- HOME
- 古本一括査定.comブログ
- 古書店インタビュー
- 第11回「ブックバンク倉吉 ~ローカルの強みを生かすネット古書店~」
古書店インタビュー
あなたの本を未来へつなぐ
2020.09.22
古書店インタビュー
第11回「ブックバンク倉吉 ~ローカルの強みを生かすネット古書店~」
「ブックバンク倉吉」が拠点を置くのは、鳥取県の中部に位置する倉吉市。店舗を持たないネット古書店を始めて、今年で9年目を迎える。
店名の「バンク」は「銀行」=「預かる」の意。お客さんから本を預かり、次の持ち主に届ける。そんな仕事に対する思いが込められている。
特に注力しているジャンルは郷土資料。商品をネット上で販売する際の書籍データの入力作業は、市内にある障害者就労支援施設に発注している。
もともとは県庁職員だった店主の佐治勉さん(36)は、どうしてネット古書店を始めることになったのか。そして、なぜ郷土資料にこだわり、障害者とともに仕事をしているのだろうか――。
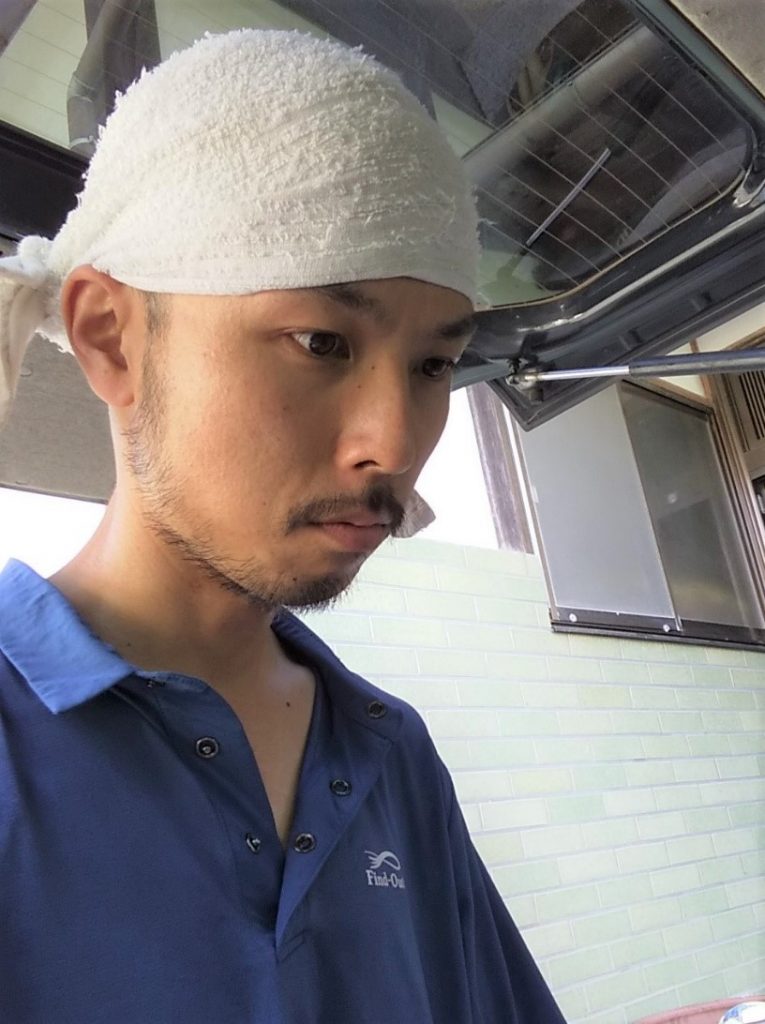
査定をしながら本を片付けている店主の佐治勉さん
古物商許可と新聞広告で、古書店のできあがり
―― 佐治さんは高校卒業後に県庁で働き始めて、26歳で退職したそうですね。古書店を始めるために県庁職員を辞めたんですか?
佐治 実はそうではないんです。「公務員になれば安泰かな」みたいな軽い気持ちで県庁職員になったんですが、いざ働き始めてみると仕事が苦痛で仕方なかったんです。ずっとわけがわからないまま働いていて、うまく消化ができないこともたくさんあって。しだいに精神的にもしんどくなってきたので「この仕事は自分には合っていないんだ」と思って、26歳の時に辞めました。
―― その後は、どんな経緯で古書店を開くことになるんですか?
佐治 少しだけ介護の仕事をしたり、親戚の仕事を手伝ったりもしたんですが、一年もしないうちに家業を手伝いながら〝せどり〟を始めました。最初は県庁職員の頃に読んでいた本や親の本を、ヤフオクなんかで売ってみたのが始まりです。
ちょうどAmazonのユーザーが増え始めて〝せどり〟が流行っていた頃で、ブックオフでまとめ買いした本が、ネットだと数倍の価格で売れちゃったりしたんです。さすがにそれで食っていけるとは思いませんでしたが、小遣い稼ぎくらいにはなるなと。
ただ、家から最も近いブックオフに行くまでに1時間くらいかかるし、行ったところで収穫がない日もあるわけで。段々「これは面倒だな」と思うようになったんです。その時に思いついたのが「だったらお客さんに売りに来てもらえばいいんだ」ということでした。
古物商許可を取って、新聞に広告を載せて、それで古書店のできあがりです(笑)。
―― 他の店での修行をしないまま、古書店を始められたんですね。
佐治 東京の「浩仁堂」(武蔵野市)さんで2日間だけ仕事の様子を見せてもらったことはありますが、他のお店で働いたことはないですね。
だから「古書店を始めた」とは言っても、特に初めの頃は買取も良かったり、悪かったりでした。新聞のローカル欄に一行広告を載せると、すぐに軽バンに山盛りの買取依頼があったんですが、ただ古いだけの本ばかりでまったく売れない、みたいな。
古書組合には加盟したものの、市内の加盟店はうち以外にはなく、これまでに県内の加盟店で集まったことも、交換会が行われたことも、一度もありません。だから、最終的に全部自分でやるしかないという考えに行き着きました。
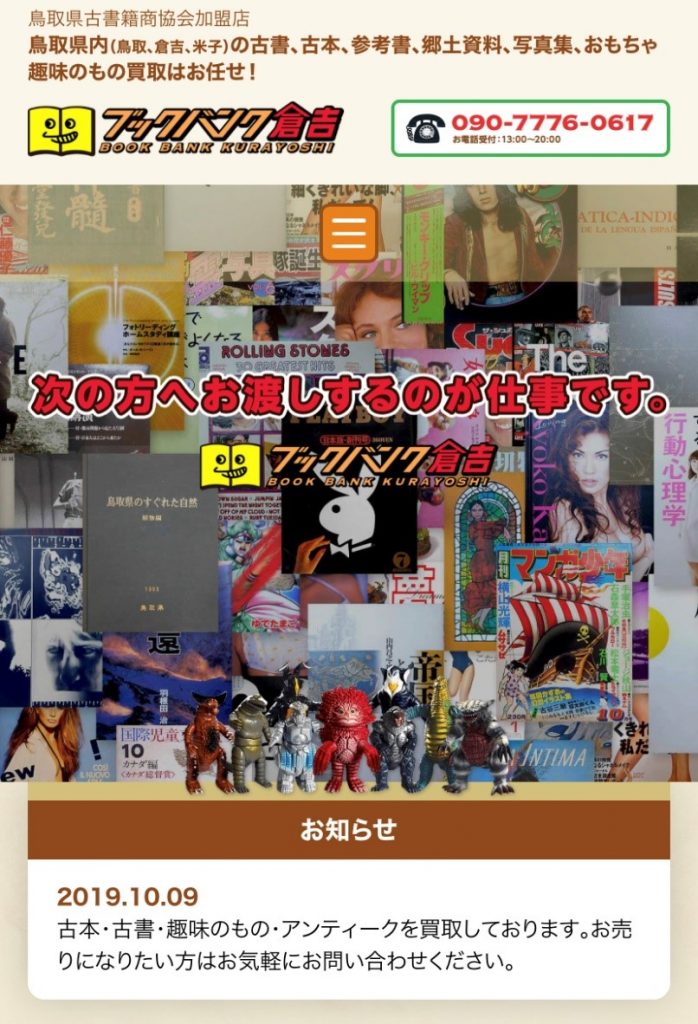
ブックバンク倉吉のホームページ
〝田舎〟ならではの広いバックヤード
―― 仕入れルートはどうやって確保したんですか?
佐治 新聞の一行広告と地域のチラシの集合広告を定期的に出しているのと、あとはホームページですね。市内にはうち以外に古書店がないこともあって、実店舗をやっていなくても結構、買取を頼まれるんです。
どちらかと言えば広告がメインで、ホームページはないよりはあった方が良いという感じです。ホームページに力を入れたところで、大手のネット古書店に勝てるわけがないし、ここみたいな〝田舎〟には新聞やチラシなどの紙媒体しか見ていない高齢者や「すぐに取りに来てくれるなら、近所の店を選ぼう」と思ってくれる人がわりと多いんです。
―― 店舗を持つことは考えなかったんですか?
佐治 えーっと、なるべく苦労しないようにしているんですよ(笑)。仮に店を持つとなると、多少の借り入れをしたり、人を雇ったり、どうしても月の支払いが膨らみがちですよね。東京とかだとなおさら。それに比べて、うちの場合は月の支払いは2つの倉庫の賃料で合わせて1万円だけなんです。基本的には「苦労しても負けるだけだ」と思ってます。
地方なので、買取が安定してあるとは限らないですし、お店を構えたところでお客さんが欲しい商品を揃えられる自信もなかったというのもあります。あと、文学全集なんかは店では売る自信はありませんが、ネットなら売れるかもしれませんからね。
ちなみに、親戚が持っている倉庫も使わせてもらっています。土地に余裕があるというのは〝田舎〟の特権ですよね。土地があると、適当に買い取って、適当に保管しておいて、時期がきたら適当に売り出すなんてやり方ができるんです。〝田舎〟の利点は、広いバックヤードが確保できるので、安い商品を積んでおいてもそこまでも負担じゃないところですね。
―― 特に力を入れられている郷土資料の買取も、地域ならではですね。
佐治 そうなんです。例えば、最近では『千歯扱き――倉吉・若狭・横浜』(横浜市歴史博物館/2013年)という本を買い取りました。「千歯扱き」というのは、稲を掻いて落とす櫛のような農具なのですが、タイトルのとおり、この本には倉吉の鍛冶職人が手掛けた千歯扱きが取り上げられています。
こういう本は、かなりの時間をかけて執筆されているにも関わらず、多くの場合は発行部数が少ないので、うっかりするとすべて処分されてしまう可能性があります。だけど、そのうち誰かが何かを調べる時に必要とされるかもしれないわけです。もちろん、高く売れる本ではありませんが、僕はそこに価値を見出しているんです。
こないだ売れた変わり種は『倉吉市 就職募集情報 1980年』というハローワークが作った本です。読んでみると、1980年時点で倉吉市にあった工場やショッピングセンターの従業員数や開業の年なんかがわかるんです。ブックオフなんかに持って行けばゴミとして処理されるはずですが、うちでは1000円で売れましたよ。きっと何かの資料として買われたんでしょうね。

バックヤードの本棚
支援とか、そういうことではなくて
―― 書籍データの入力作業を障害者の方々に発注されているのは、どうしてなんですか?
佐治 きっかけは「浩仁堂」さんで仕事を見せてもらったことですね。「浩仁堂」さんのお店で障害者の方々が働いていたんです。
冒頭でもお話したように、県庁で働いていた頃はとにかく仕事が苦痛で仕方ありませんでした。だけど「本当はもっと仕事がしたい」という思いはずっとあったんです。うまく説明できないんですが、公務員の仕事が自分にうまくはまってない感じがしてたというか、とにかくいつも空回りしてたんですよね。
「浩仁堂」さんで障害者の方が働かれている様子を見て、「仕事内容さえ工夫すれば、働き手の働きたいという気持ちは実現するんだ」と思ったんです。例えば業務を細分化したり、体系立てたりするなどして、働き手が求めるやり方に合わせることも可能なんだと。公務員の仕事に自分を合わせることができなかった経験があったから、そんなふうに感じたのかもしれませんが。
ちょうど、僕も一人では仕事が回らなくなってきていたし、データ入力であれば、内職としてやりたい障害者の方がいるだろうと思ったので、障害者就労支援施設にお願いしてみたんです。
―― 公務員時代の苦しい経験が、障害者の方々を支援したいという思いにつながったということですか?
佐治 支援とか、そういうことではないんですよね。障害者であれ、健常者であれ、仕事の内容を上手に働き手に合わせることができれば、どんな人でも価値を生み出せるし、お金を稼げると僕は考えています。支援しているのではなくて、一緒に仕事をして、お金を稼いだり、お客さんに喜んでいただいたりしているだけです。
もちろん、障害者のなかには真面目に働いてくれる人もいれば、「おいおい、ちゃんと働けよ」と思う人もいますけどね(笑)。それは健常者でも同じですから。
今、うちでは6人の障害者の方が働いてくれていますが、僕は彼らのことを普通に仕事上のパートナーと思っています。障害があっても、できる仕事はいっぱいある。そんな考えがもっと広がっていけば良いなとは思いますね。
ブックバンク倉吉
一括査定内ページ:https://books-match.com/shoplist/detail?id=83
HP:https://www.bookbank-kurayoshi.com/
安心して信頼できるお店へ買取依頼できるサービス「古本一括査定.com」
